 |
 |
1928年製ツェッペリン飛行船の船首部
この大空の巨鯨といってよい飛行船が
ニューヨーク着陸の際、爆発炎上したシーンは
皆さんもどこかでご覧になったことがあるはずです。 |
フォッカーDⅠ
1917年夏参戦、
最もよく知られた第一次大戦時の戦闘機のひとつ
赤く塗られた機体はレッドバロンと呼ばれ、
リヒトフォーヘン男爵の指揮下で戦った。
3葉構造の為、操縦性、上昇力、旋回性能が
良い反面、低速であったため、
1年後には後継機と交代した。 |
 |
 |
ルンプラーC Ⅳ 「タウベ」
1917年制式採用の戦闘機、機銃は後席の銃架に取り付けられます。
まだまだ木と紙で出来た凧の面影が、色濃く残っています。
この後、戦争が飛行機を鍛え、あっというまにたくましい面構えに変っていきました。 |
 |
 |
メッサーシュミットM17輸送機
1927年製、金属構造主流になってゆく過渡期の機体でしょうね。
⇒正確にはM17スポーツ機、でした。
1925年製造、全木製で大変軽量であり、s15グライダーをベースに、僅か27馬力のエンジンを積んでいます。
沢山の競技に出場し優勝、メッサーシュミットに、初の自前の工場建設資金をもたらしたのだそうです。
バンベルグからローマまでアルプス中央部越えを敢行し、軽飛行機として初めて成功しました。
メッサーシュミット先生、大変失礼いたしました。
M17機、失礼しました。(礼!) |
 |
 |
ユンカースF13 全金属旅客機
1920年就航、世界初の実用全金属旅客機として登場した。
全欧で旅客輸送の増大にこたえた。 |
 |
 |
ひだり、ユンカースA50
波型金属板の使用により軽量化に成功した全金属単葉機
1930年には日本人パイロット吉原が、東京ベルリン間を10日で飛行している。
みぎ、ユンカースJU 52 全金属輸送機
第2次大戦中の主要輸送機として大量に戦線に投入された。 |
 |
 |
ドルニエDoX
1929年就航の翼長48mにおよぶ大型飛行艇、 欧州から南北米大陸を結んだ。
右は当時のルフトハンザのポスター。 |
 |
 |
ドルニエ「リベレ」小型飛行艇
1929年製
なんとも優雅な姿態です。
|
フィーゼラー「シュトルヒ」観測機
第2次大戦中、草地での短距離離着陸性能から、
様々な用途に使用された。
機体は、戦後のスイスバージョン。
雪上着陸が可能なスノーシューを装着している。 |
 |
 |
メッサーシュミットMe109
第2次大戦を代表する戦闘機のひとつ
この機体の迷装は北アフリカバージョンかなあ…
(「撃墜王アフリカの星」という映画が昔ありましたね) |
 |
 |
 |
 |
メッサーシュミットMe262
1944年から量産機が実戦配備についた、世界最初の実用ジェット機。
1942年初飛行した。 |
 |
 |
メッサーシュミットMe163B
ロケット迎撃機、1939年初飛行、1944年から少数の機体が実用に供された。
最大速度は音速を優に越え、12000mまで3分あまりで上昇できる。
日本の秋水は基本設計図をドイツから供与され試作されたもの。 |
 |
 |
V1とV2
V1はシンプルなラムジェットエンジンを使用していたが低速のため撃墜されることが多かった。
V2は本格的な液体燃料ロケットで、その技術は大戦終了後米露に技術者ごと移転され、
今日のロケット技術の礎となっている。
両者によるロンドン空襲は大きな被害を出した。 |
 |
ひだりは、ある飛行機の後姿です。
たぶん名前はないと思います。
この飛行機は、東独から脱出した家族が
スクーターのエンジンを使い自作したものです。
たしか5人が大きくない胴体にもぐりこんで
脱出に成功したと思います。
たぶん飛行試験なぞ不可能だったでしょうから、
ぶっつけ本番で離陸したのでしょう。
よくも無事に飛行できたものだとビックリしました。 |
これからの3枚は、グライダーの機体です。
欧州、特にドイツではスポーツ航空が
現在もそうですが、大変盛んでした。
日本でも輸入されて、ポーランドなど欧州製の
軽快なソアラーが沢山活躍しています。
皆さんもきっと何処かで
欧州製の機体を目にしていますよ。 |
 |
SG38 プライマリー
1923年から生産されたもの。
ベルサイユ条約で軍備が禁止されていた中、
グライダークラブのメンバーは、軍事パイロットの
予備軍として養成されていった。 |
 |
 |
VANPYRグライダー
1921年製
飛行性能はどうだったか知りませんが、
3点式のゴムタイヤの形がとてもユニークです。 |
スパッツ複座セカンダリー
1952年東独のダッハウで製造、500機を数える
このあとグライダーでも
スチールパイプ構造の機体が主流となった。 |
 |
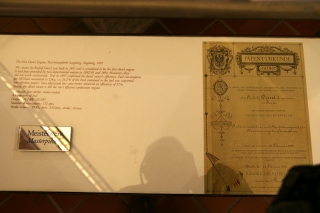 |
世界最初のディーゼルエンジン
ルドルフ・ディーゼルによって、1892年から97年にかけて発明、改良された。
右はその「特許証」、1893年、皇帝立特許局ベルリン発行とある。 |
以上で本館のツアーは終わりです。
足を引きずりながら、建物の外を出ると、
こんな時計盤が目に入りました。
文字盤が黄道12宮になっているのは分かりますが、
その下にある小さな円盤には
何やら昔の神々を飾ってあるようです。
7つの神々で何を表すのかなあ、指示針もあるし…
(曜日かなあ?) |
 |