2009年9月27日 「栂池に紅葉を見に行ってきました」
2009年9月20日 「いよいよ秋ですね、何はなくとも近況を…」
2009年9月3日 「今度は後立山の唐松岳にチャレンジ」
2009年9月27日 「栂池に紅葉を見に行ってきました」
先週のシルバーウイークがあけた24日、午前中は天気がよさそうなので思い切って出かけました。
2年ぶりなので、一寸早い紅葉が楽しみです。
残念ながら9時には雲がひろがり始め、白馬三山を隠してしまいましたが、素晴らしい風景に大満足でした。
紅葉の頂点とおぼしきタイミングと、快晴に恵まれた前回の時と比べても十分に堪能しました。
二度と同じ風景はないのですから…
「風景と花々」のページに「栂池紅葉① 風景編」を追加するので、そちらをご覧いただくとして、ここでは簡単に
ルートをご案内したいと思います。
それから、次回、「栂池紅葉② 葉っぱ編」を追加いたします。そちらも是非ご覧ください。
| このページのトップへ | 次の話題へ | 前の話題へ |
2009年9月20日 「いよいよ秋ですね、何はなくとも近況を…」
ええ、毎度ご無沙汰しております。
うかうかしている内にあれからもう半月が経ってしまいました。
退職生活にどっぷり浸かってしまったせいか、雑事にうかうかと過ごすうちに毎日が飛ぶように過ぎてゆきます。
この調子だと何もしないうちに冥途へ旅たつ日を迎えそうです。
実は今年の正月に願掛けをしまして、①写真展をやる、②ホームページをおこす、③ゴルフのスコア100をきる、でありました。
おかげさまで最初の2つは実現できたのですが最後のやつが大分難問です。
ゴルフ歴だけは長いのですが、生来の運動音痴ゆえベストスコアはこれまで108でした。
(なぜかお釈迦様のおっしゃる煩悩の数と同じ)
ここ数年は120~130と皆に呆れられながらのプレーでした。
それでも運動と言えばゴルフくらい、ということなので、仲間にいやがられない程度には上達しておこうと、
にわかに練習所通いを本格化させたのでした。
特にこの半月ほどは、半日練習場、半日庭で草取りという、世のまっとうな皆様からみれば信じられない毎日を過ごしています。
成果は? まあ人生何事も長い目でみましょう…と、何方かおっしゃって居られませんでしたかね。
ええと、話題を変えて、今日は塩尻市で昨日あった「鳥のわたり」という講演会のお話をします。
講師は林さんという野鳥の会の諏訪支部長の方で、昨年春、岡谷の小鳥バスに参加したときガイドをつとめられておられました。
ところで、ワシやタカの渡りは大変見事なものなのだそうです。
渡りには鳥の種類ごとに決まった場所があり、そこで各々上昇風をつかまえて高度を高く取ってから、
高空の渡りの道といわれる決まった高度、方向を、群れが一本の筋となって飛んで行くそうです。
(そういえば今月はじめ、松本市奈川で観察会があったような…)
このお話を伺いながら、「どこかで見たような」と思ったのでしたが、帰りの車の中で思い出しました。
ちょっと古い話で恐縮ですが、アニメの宮崎監督の作品の中に「紅の豚」というふざけた題名のものがあります。
(作品としてはよくできていますよ)
そのなかで、第一次大戦中、欧州の航空戦で撃墜された戦闘機がプロペラの回転を止めたまま、雲の上に次々と
浮かび上がってくるシーンがあります
そのはるか上空には一筋の流れが見え、よくよく見ると、それはこれまで撃墜された飛行機たちのたくさんの残骸が、
一連なりになってゆっくりと遠くへ消え去ろうとしているようです。
今雲を突き抜けてきた残骸たちも、死んだ操縦士たちを乗せたまま、その一筋の流れに加わるべく上昇を続けるのでした。
初めてこの作品を見たとき、これは仏教でいう生と死の境、彼岸と此岸の寓意だな、雲はまあその境の三途の川か、
と思ったのでした.
今回、図らずもワシやタカの渡りの姿にも重なることを知って、これはもう必ず見なければならない、と心に決めたことでした。
今回は写真もなく、お話ばかりが長くなって退屈されたろうと思います。
これに懲りずに次回をお楽しみに、たぶん栂池か千畳敷カールの紅葉ですよ。
| このページのトップへ | 次の話題へ | 前の話題へ |
あれだけヨレヨレになって苦しい思いをした、八ヶ岳の硫黄岳登山から一月も経たないのに、
今度は唐松岳にチャレンジしてみました。
ボケが進んだせいか、つらかったことは全部忘れてしまい、頂上に立ったときの達成感や雄大な風景、
全身を吹き抜ける高山の風、そんなことばかりが思い出されて、寒くならないうちにと、いそいそと
出かけたのでした。先週金曜日の8月28日のことです。
お仲間は前回と同じく友人と2人です。前回の経験から友人も十分心得ていてくれて、ゆっくり
私のペースにつきあってくれました。
お盆が過ぎて山のハイシーズンも終わり、リフトの営業開始時間が1時間半も遅くなっていたので、
頂上までいけるのか正直心配でした。まあ行ける所まで行ってみよう、最終のリフトに間に合わなかったら
小屋泊すればよいやと、退職者は気楽なものです。
八方池までは何度か上がったことがあるのですが、それから先、丸山ケルン、唐松山荘、唐松岳頂上は
初体験です。帰りのリフト時間もあり、私としてはかなり飛ばしたつもりでしたが、息が上がってしばしば
立ち止まらざるを得ないのは前回と同様でした。
期待したお天気のほうは、雲があって頂上部はガスッたままで残念でしたけれど、風もなく最後まで
もってくれたので助かりました。
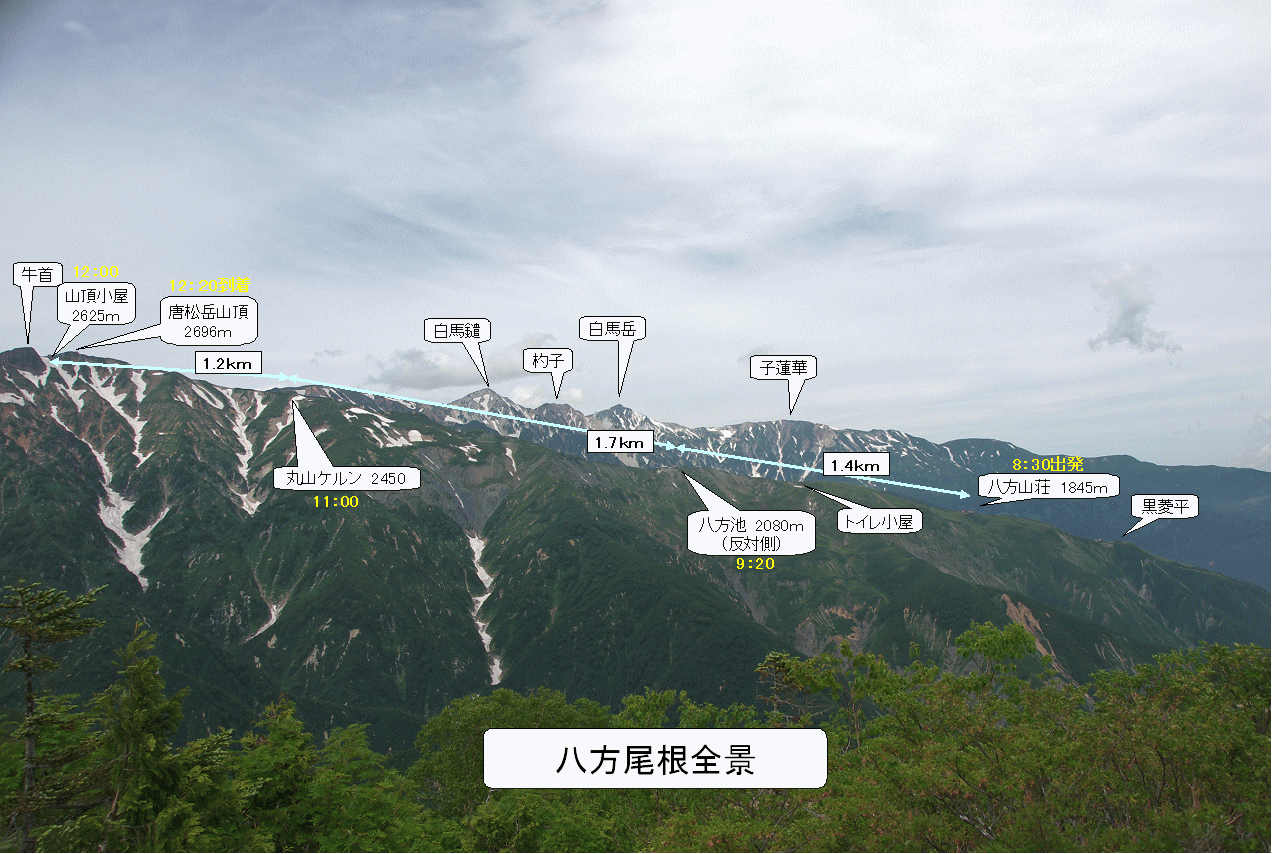 |
(上の写真は7月に五竜につづく遠見尾根の小遠見山から撮影したものです。)
朝8時半に八方山荘前を出発し12時20分に頂上に立ちました。12時40分に頂上から下山開始、
八方山荘前のリフト乗り場には15時45分に着きました(リフト最終は16時半)。約7時間の山行でした。
ゆっくり周りの風景や撮影を楽しむ時間(と体力)がなかったのは残念でしたが、ときおりガスが
晴れた時にひらける、頂上からまじかに見おろす不帰の嶮は素晴らしかったです。
八方池からでは見上げるものを、見下ろしたんですからねえ。
お山はもうすっかり秋で、秋の花々が豪勢に我々を迎えてくれました。
白馬はやっぱりお花の種類も数も、他に比べて圧倒的に多いように思います。
今回は時間に追われていたせいもあって、持参したカメラのレンズのフタを取る余裕もありませんでした。
(やっぱりヨレヨレだんったんです)
従いましてこれからご覧をいただく写真は、前回と同じく全部友人の手になるものです。
Kさん許可してくださって有難うございます。
やれやれ、いつになったら山頭火の「分け入っても分け入っても青い山、うしろ姿のしぐれてゆくか」
という具合に、格好よく登れるのかなあ。
| このページのトップへ | 次の話題へ | 8月の話題へ |